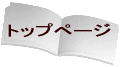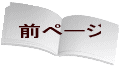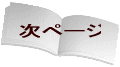| 近大総監督 松田博明 ”Talk”and Talk 泣き笑い指導者論(4) |
| 「攻撃野球」の原点に立ち、ついに悲願の大学日本一に 近大野球部を率いて40年目、夢にまで見た大学日本一の栄冠を手にする時がついにやって来た。昭和63年春の全日本大学選手権で松田近大は悲願の初優勝を遂げる。血のにじむような猛練習で培った攻撃野球が、しっかりと根を張り、大輪の花を咲かせた。翌年も連覇を果たし黄金時代を近大は築くのだった...。 |
|
| ●バット片手に選手を追いかけ回し、試合を中断させたことも・・・ | |
| ベースは野球の塁のほかに「基地」とか「根拠地」と和訳されています。野球は相手の堅固な守備陣に攻撃を加えて突破。基地を次々に占領して生還するという「陣取りゲーム」です。だから強烈な攻撃力がなければ相手の守備陣を突破することはできません。 近大野球の身上は「撃ちてし止まむ」の攻撃野球。ところが、昭和60年、関西学生リーグの覇者となって大学選手権の関西代表を決める試合に臨んだのですが、決定戦で近畿リーグ代表の阪大に敗れてしまったのです。このことは先月号にも述べましたが、それからというもの連日、連夜にわたって大学野球ファンと称する人たちから私の自宅、野球部寮に電話がかかってきたのです。「阪大なんかに負けるとは何事ぞ。しっかりせんかい」こういう内容が大半。これが私や部員にとって“発奮剤”になったのです。 これも先月号に書きましたが、7月1日から18日までの再起を期しての練習では従来使ってきた3台のマシンを8台に増やし、連日にわたって4㌧トラック1台分の球を打たせたのです。 「オヤジもずいぶんと無茶なことをするな。部員は相当しごかれとるのと違うかね」 「若いころのオヤジに戻って阿修羅になっとるんでは。部員はバッドで尻をいやというほど叩かれとるやろなぁ」 かつての教え子たちは、そんな話をしていたようでした。 たしかに血気盛んなころ、アドバイスをしても、それがいつまでたってもできないとなるとバットで部員の尻を叩いたことはずいぶんとありました。北陽の監督をしていた松岡英孝君は昭和35年の卒業生ですが、聞くところによると練習の際はスライディング・パンツを2枚重ねてはいてたそうです。バットで叩かれたときの衝撃を少なくするための防御法だったとか。 またリーグ戦で、とんでもないミスを犯した部員を攻守交代でベンチに戻ってきた時、バットで尻を叩いてやろうと思っていると、彼がグラウンドへ向かって逃げ出し、それを私が追っかけて、この間、試合中断というような恥ずかしいこともしました。 これらを知っている教え子たちが自分の学生時代を思い出して、私が同じようなことをやっていると思ったのではないでしょうか。しかし、当時は“発展途上”。それに私も“年輪”を刻んでいるせいか、グラウンドでの対話重点主義をとっていたのをかつての教え子たちは知らなかったのではないでしょうか。 部員は阪大に負けた“汚名返上”で一生懸命。私もまた彼らと一体になっていました。 「こういう練習は、やがて効果を発揮するだろう。現役から後輩へ、さらにまた次の世代に・・・・・」。 取材記者のインタビューを受けた際の話です。スポーツの世界で「練習は根。試合は花」という言葉があります。しっかりと深く、そして広く根を張らなければ花は咲きません。たとえ、咲いたとしても大輪の花ではありません。私と部員は阪大に負けたことを大きな明日の糧にしようと誓ったのです。 やがて、昭和60年7月の原点に立ち戻っての練習が点となり、それが線を引き、63年につながっていったのでした。 |
 バットで部員の尻を叩くほど血の気が多かったころの松田監督(左から2人目) |
| ●”風雪40年”の栄冠は手にして見ればあっけなかった・・・ | |
| 昭和63年春のリーグ戦で3季連続、旧関西六大学時代から数えて通算19度目、関西学生リーグ10度目の優勝を達成。大学選手権の関西代表決定戦をも制覇して、東上することになったのです。 左の酒井光次郎(松山商出、現日本ハム)と右の西原英基(箕島高出、現ヤマハ)の3年生投手に、内野には岡本圭治(岡山東商出、現阪神)、十河章浩(高知高出、現日本生命)らがいましたが、全体的に小粒なチームでした。 私と近大野球部が東上しますと、東京六大学のある監督はかつて、こういったものでした。「まだ関西にいるのか」と。この一言がいつも私の「打倒東京六大学」への闘志をかきたてたのですが、過去3度、決勝へ進みながら目標を達成することは出来ませんでした。 この昭和63年も決勝へ進んだのですが、8回表を終わって0対1と東北福祉大に封じられるありさま。前年は山内嘉弘(茨木東高出、現オリックス)がいながら準々決勝で、この東北福祉大に敗れたこともあって、全員が必勝を期していたのですが、1点が返せないまま8回裏に入ったのです。この回、私はよく投げていた酒井を引っ込めて代打を起用しました。が、この代打が倒れ、やがて走者が出たものの二死三塁。打席に入ったのが十河。彼は左翼席へなんと逆転の2点本塁打を打ち込んだのです。 “起死回生”どころではありません。彼の一撃は、まさに“回天”といえるものでした。 この時酒井はアンダーシャツを着替えようと上半身、裸になっていたのですが、うれしさのあまり、裸のまま十河を迎えに走りだしていましたねぇ。十河の逆転本塁打は、私にいわせればまさに執念の一撃だったように思います。 彼の一撃に続いて連打が飛び出して追加点を挙げて、3対1のスコアで、ついに悲願にしていた日本一。いざ、大目標を達成してみると、なんとあっけないことか。 「私は日本一に近大を押し上げられないままに辞めていかなければならないのか。いつの日、日本一になれるのだろうか」。 過去16度の大学選手権で敗れるたびにそういう思いをしてきました。それが、いざ目標を達成してみると、それは“風雪40年”にしては、あっけなかったのです。 「胴上げされた瞬間、ああ終わったなと思ったよ。これでは辞めないかんなぁ。考えてみると、このチームでよくもまあ日本一になれた」。 優勝後の記者会見で私は、そういいましたが、これは偽りのない胸中でした。要するに、このチームは過去に大学選手権に出場したどのチームよりも力がなかったのです。それでいて日本一になれたのは粘りと最後まで近大野球の原点である「攻撃野球」。打って打って、相手基地に攻め込んでいくことを忘れなかったからでしょう。 |
 昭和63年の大学選手権、4度目の決勝進出でついに初の覇権を握る。 |
| ●平成元年から肩書きが総監督になり、前年に続いて大学選手権V | |
| 過去を振り返るのは大嫌いな方ですが、優勝の夜は珍しく思い出にふけったのでした。 有藤道世君(高知高出、元ロッテ監督)がいた時代、スプリング・キャンプを高知でしたことがありました。が、予算が足りなくて高知市内の大きな病院の看護婦さんに毎晩ダンスを教え、その謝礼を合宿費に当てたこと。また、ある年の高知キャンプでは旅館に支払いができなく、急きょ秘かに大阪へUターン。父親に黙って土地を売り飛ばし、その金を持って高知に戻って旅館の支払いをしたことなど・・・。ゴルフの会員権を片っ端から売って合宿費や遠征費に使ったこともありました。思い出は尽きませんでした。 「この日本一を無駄にしてはならない。これを点とし、やがて太い線を描かなければ・・・。喜んでばかりおられん。後が大事」。 そういう訳で、秋の明治神宮大会の優勝を目標にし、秋のリーグ戦にも優勝したのですが、昭和天皇がご病気中で大会は自粛中止。事情が事情だけに中止はやむを得ないものでした。 そして平成元年春、秋は肩書が監督から総監督へ。しかしベンチで指揮をとり、リーグ史上初の5連覇、2度目の10連勝で近大野球部は“完全V”を飾ったのですが、優勝を決めた立命との2回戦は2対2のスコアで迎えた延長14回表、近大が3点をあげて5対2で勝ったのです。 酒井が健在。右の西原も成長していましたし、打線も充実していましたが、果たして関西代表決定戦を勝ち抜いて大学選手権で“連続日本一”になれるだろうかと心配していました。指導者というものは、あれやこれやと考えるものです。関西代表決定戦で代表となったのち、大学選手権の舞台は神宮球場ではなく、グリーンスタジアム神戸でした。 酒井はリーグ戦から無失点記録を続けて、近大は決勝で専大と対決したのです。酒井は疲れていました。「総監督。酒井はへばっております。無理なようなので西原を先発させてはどうですか」 捕手が私に訴えてきました。が、捕手の助言を一蹴しました。 「疲れとるのはわかっとる。酒井が打たれて負けるんなら、みな納得やろ。酒井でここまで勝ってきたんだから」。 ところが1回、町田公二郎君(現広島)に1回二死三塁で左前安打され、酒井の無失点記録は80回1/3で切れてしまったのです。 その裏の攻撃で3点を奪って逆転したのも束の間。3回にはまたも町田君に今度は逆転の3ラン本塁打を浴びてしまいました。これでは続投させることはできません。そこで酒井を引っ込めたのです。 野球はエースが打ち込まれると敗戦をまず覚悟しなければなりませんが、当時の選手は違っていました。 「エースが打たれたんやから、こっちも相手のエースをつぶしたれ」というガッツを持っていました。 中盤から積極的な攻撃を展開。岡林君(現ヤクルト)らを打ち込んで、終わってみれば10対7で“連続日本一”に輝いたのです。 |
 グリーンスタジアム神戸で行われた平成元年の大学選手権でも優勝(後方)が最後を締めくくった。 |
| ●「東京に負けるか」の思いが、すっかりナインに浸透していた | |
| それにしても酒井はリーグ戦でも大学選手権でも獅子奮迅の働きをしながら優勝の瞬間はマウンドにいないのです。 前年も、この平成元年の大学選手権でも“胴上げ投手”といわれる投手になったのは西原。これも巡り合わせでそういうことになったのだけれども、酒井は、一度でいいから優勝の時にマウンドに痛いという希望がどこかにあったのではないでしょうか。 そこで秋のリーグ戦で6季連続優勝をして関西代表決定戦を勝ち抜いて明治神宮大会に出場した時、本人は胴上げ投手を狙っていた節がありましたよ。 この大会は順調に進んで決勝で立教と対戦したわけですが、私は翌年のことを考えて門脇太(近大付)を使いました。彼は9回二死まで立教を5安打に抑えて完封ペース。しかも2点のリード。ところがドタン場で1点を失ったので、酒井を送り出したのです。 彼は喜びいさんでマウンドに行きました。そして優勝の瞬間、はね回っていました。彼は念願を達成したわけです。 近大は平成元年のシーズン、春秋“日本一”になったのですが、このチームをじっくり観察すると技量もさることながらチームワークという点では一番しっかりしていたと思います。 私は俗にいう“即戦力”の者よりも将来性豊かな者を辛抱して使い、育てていくことを方針にしていて、リーグ戦で勝つことも大事だけれども、リーグ戦をまじえながら選手を育成することに重点を置いてきました。これが、大学日本一に、そして春秋日本一につながっていったと自負しているのですが、やはり「東京に負けるな」という私の思いが、関東勢と対決を重ねるにつれ、選手たちに浸透していったとも考えているわけです。 「東京に勝つには近大の攻撃野球で-」。 これが私の狙い。野球は打ち勝たなければおもしろくありません。相手の防御に阻止されても、また阻止されても粘り強く攻め続けて、最後は破壊してしまう。そういう野球が一番面白いのではないでしょうか。 よく「野球は教育の一環」という人がおります。しかし、野球はあくまでスポーツの一競技種目。それを教育と結びつけてしまうのはいかがなものか。私は、よくこういうのです。 「私は教育者ではない。野球を通して教育をしようとは考えていない。社会に出て野球をしていたことで、プラスになればそれでいいのでは」。 この持論に異論もあるかと思いますが、私は「野球はあくまでスポーツ」というのが基本です。これまでこの信念に基づいて教え、鍛えてきたわけです。 |
 連続日本一の立役者となったのが、左腕エース・酒井光次郎投手(現日本ハム)だった。 |