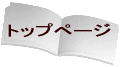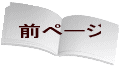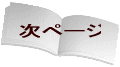| 近大総監督 松田博明 ”Talk”and Talk 泣き笑い指導者論(3) |
| 関西学生野球連盟に加わり、決意も新たに再出発 昭和38年秋、関大の西川投手がリーグ戦中に広島球団と契約を結んだ「西川事件」は、関大の優勝取り消し、出場停止という大問題となった。その際、関大の除名を求める声に断固として反対したのが近大。その18年後、このいきさつは、関六分裂、新リーグ創設の際のかすかな伏線となった−。 |
|
| ●”関大を除名せよ”の声に最後まで反対した「西川事件」の思い出 | |
| 関西大学野球連合下の関西六大学リーグを始め各リーグは、連合が創設された昭和37年以来、順調に発展を続けていました。 ところが、あろうことか、関西六大学リーグで“衝撃の事件”が起こったのです。それは昭和38年秋のリーグ戦で優勝した関大が引き起こした事件でした。関大を優勝に導いた一人である西川克弘投手が広島球団と契約を結んでいたことが明るみに出たのです。 シーズン後の契約なら問題はありませんが、契約をしたうえでリーグ戦に投げていたのですから、これは大問題。しかも西川投手だけでなく、もう1人、雑賀内野手も契約をしていたのです。これが大学野球に汚点を残した「西川事件」です。当時の新聞報道によれば、西川投手が「プロでやってみたい」といっているのを広島球団の西野襄育成局長(のちに代表、故人)が耳にし、秘かに西川投手と会い、契約を結んでいたというものです。 この「西川事件」に関西六大学リーグは狼狽。関大側では予期せぬ事件に連日、連夜にわたって会議が行われたようです。 連盟もまた会議が毎日のように深夜まで続いたのですが、この席で「関大を除名せよ」という強硬な意見もありました。同大の渡辺博之監督(故人)もその1人。 「大学野球界で前例のない事件を起こした以上、連盟としては毅然とした態度で臨まなければならない。断固として除名処分にするべき」 渡辺さんは、このようにいって、関大の除名を唱え、これに同調する大学も出できました。 関大は重いペナルティーを覚悟していたようですが、除名までは考えていなかったのではないでしょうか。だから、問題が表面化すると、関大は除名処分だけは何としても免れなければと、私に相談を持ちかけてきたのです。 「関大の除名には反対。ただし、優勝を取り消して最下位とする」これが私の持っていた善後策でした。なぜ、私は除名に反対をしていたのか−。 それは関大が東の東京リーグと並ぶ古い歴史の関西六大学リーグの発展に大きな貢献をしてきたうえ、関西六大学リーグの入れ替え戦制を盛り込んだ関西大学野球連合を創設するに当たって先頭に立ち、近畿、阪神、京滋の各大学リーグに“陽の当たる場所”に出るチャンスを与えてくれたからでした。 「松田さん、何とか関六に残れる方法はないものか」関大関係者は悲痛な声でした。 私は連盟での会議で「関大の除名は避けなければならない」と訴えたのです。これが通り、関大は除名をされずに済みました。ペナルティーは優勝を取り消し、さらに翌年春の出場を辞退ということになりました。 この時、関大の除名を救ったことが、昭和56年秋のリーグ戦後に関西学生野球連盟を創設するさい、近大がこの連盟に入る一つの遠因になったのではないでしょうか。それというのも関大が「新リーグに近大を入れなければ」と力説したそうです。 |
 関大・西川克弘投手(写真)が、リーグ戦中に広島と契約を交わした「西川事件」は、大学球界、プロ球界を揺るがす大騒動に発展した。 |
| ●旧関西六大学分裂、そして新リーグ「関西学生野球連盟」誕生 | |
| 関西学生野球連盟が創設されて、スタートをしたのは昭和57年春のリーグ戦。この前年から関大らが「大学野球本来の姿である対抗戦に戻そう」という動きをしていました。「対抗戦にする」という事は、「入れ替え戦制」の廃止。つまり昭和37年以来続いてきた関西大学野球連合の解体にもつながってきます。 こうした動きの中で行われた56年秋のリーグ戦は近大が優勝。関大、同大、大商大、立命という順位でした。立命は最下位ですから入れ替え戦に臨まなければなりません。 入れ替え戦の立命に挑戦したのは3リーグの優勝校、京滋代表の京産大。この京産大に立命は負けてしまいました。京産大が関西六大学リーグ入り、立命が京滋リーグ行き。そういう事になったのですが、これは新連盟の創設によって“幻”となりました。 新リーグは関大、関学、同大、立命のほかに京滋リーグに落ちていた京大、それに近大を加えて創設しようという線で固まり始めました。「近大は我々の仲間に入って一緒にやってもらう。近大抜きではやれない」 こう力説したのは関大でした。が、リーグ戦4位の大商大をはずす事に私は反対でした。だから、近大に新しいリーグに入るように要望があったとき、大商大も何とか加えてほしいと申し入れました。さらに私はいったのです。 「大商大をいれられないというのなら近大は出身リーグの阪神リーグへ戻る。私はあくまで筋を通したい。なぜ大商大をはずすのか」。 旧関西六大学の関大、関学、同大らはそれでも大商大をグループに入れる気持ちはありませんでしたが、近大が離れることに猛反対でした。最終的に、私と近大は断腸の思いで大商大と袂を分かったのです。 入れ替え戦で立命を倒した京産大もまた気の毒でした。関西六大学リーグ入りを果たしたというのに分裂寸前だったからです。京産大側は怒りを込めて発言しました。 「関西六大学リーグから離れようとする大学は脱退になる。脱退していくのだから、関西六大学野球連盟の名称は我々が継承する。」この発言は当然のことです。結局、関大、関学、同大、近大、それに立命、京大によって新リーグを創設する運びとなったのですが、さて、どんな名称にするか、いろいろと案が出ました。 記憶しているものを挙げますと「新関西六大学野球連盟」に「関西学生六大学野球連盟」、そして「関西学連野球連盟」というものもあり、そのほかに、途中でひと息いれなければいえない長い名称も、かなりありました。最終的に「関西学生野球連盟」に決定。新しい一歩を踏み出したのです。 |
|
| ●大学選手権代表決定戦よりもリーグ戦の開会式に出るのが筋だ | |
| 話がわき道にそれましたが、近大は旧関西六大学リーグ入りをして以来、脱退までの間、最下位になったことはあっても、近畿リーグに戻るような事は一度もなく、このリーグで春秋通算9度の優勝をしたのですが、旧関西六大学最後の年となった昭和56年は忘れられません。 41年の春のリーグ戦で優勝して以来、念願の一つだった春秋連覇が始めて達成できたからでしたが、ラストシーズンの秋は、現在もなお私の脳裏に焼き付いています。このリーグ戦で関大と史上11度目の優勝決定戦を交えたのです。 試合は、近大が3、4回に各1点をあげて有利に展開していたのですが、8回に1点差に追い上げられたうえ、9回には同点の本塁打を打ち込まれてしまいました。やがて夕陽が西に沈み、延長10回からナイターになりました。 押していても決勝点が奪えず、ピンチを脱出しても、また走者を出すというありさまで、回は15回、さらに16回に入っても勝負はつきません。やがて17回に入り、関大の攻撃を阻止したあと、近大は二死三塁に走者を出しましたが、私は得点が入るとは思いませんでした。それが失策によって決勝点を拾い、サヨナラ勝ち。私にとって、延長17回を戦ったのも、3時間43分という長時間試合も初体験でした。 「優勝する事がこんなに苦しいものだということを選手が体験した。これは大きなプラス。それにしても関大の気力はすごかった。私が想像していた以上に迫力があった」 報道陣に優勝の感想を求められた私は、そういう話をしたように思います。これは本当に率直な感想でした。 旧関西六大学リーグの最初の入れ替え戦でリーグ入りをし、最後のシーズンが春秋連覇。57年の春にスタートした関西学生野球連盟最初のリーグ戦でも近大は9勝2敗、勝ち点4で最初の優勝校となったのですが、大学選手権となると、目標の“覇者”の2字は、いつも山の彼方、雲の果て−。あと一つの山がなかなか越せません。 大学選手権で思い出されるのは関西六大学リーグ時代の昭和49年の第23回大会が札幌丸山球場で開催されたときのこと。飛行機で行ったのですが、負けたこともあって函館港から新潟まで船。そこから汽車で帰らせたのです。 また、こんな事もありました。昭和57年春のリーグ戦で優勝。大学野球選手権の関西代表決定戦に出場することになったのですが、この決定戦が5月31日から。ところが、最終節の立命一同大戦が3回戦にもつれ込むと、閉会式が代表決定戦にぶつかるわけです。連盟としては、この場合、決定戦への出場辞退を決めていました。これは当然のことで、私をはじめ、近大側もそのつもりでした。 「リーグの全日程が終了せずに代表決定戦に出場するのは、リーグ戦主体の連盟を結成した趣旨に反する」というのが私の考えでもあったからです。関西学生野球連盟を創設するに当たって、「学生野球の本来の姿は対抗戦にある」という趣旨だったのですから・・・・・。 ところが理事会で「リーグ戦の未消化を理由にした辞退は好ましくない」と辞退から出場へ方針が変更されていたのです。このことは私の耳には入っていません。そこで、私が正論を唱えたので、連盟側は驚いたようです。 私は大学野球のために筋を通そうとしたのですが、連盟の組織の中の近大である以上、従うほかはありませんでした。 |
 昭和56年までの旧関六で、近大の優勝は9回を数えた。 |
| ●阪大にまさかの敗戦・・・猛暑の中、地獄の1万本打撃を敢行 |
|
| この年の前年、大学野球選手権の決勝で明大に2対8で完敗。そして58年には、またも決勝で今度は駒大に1対5。守備固めに起用した二塁手の失策で1対1のスコアだったのが1対2となって、8回に致命傷の3点を失い、敗れました。「優勝の原因は一にも二にも“守りの中の攻め”。要するに守り勝ち。打力のよい近大を阻止できたからね」。 優勝監督となった駒大・太田誠監督の言葉が私の胸に突き刺さったものです。なにしろ、こちらは守りのミスが敗因の一つになったのですから。この太田監督と私はウマの合う仲間なんです。こちらは道楽というか、野球以外に好きな物がないし、太田監督にいたっては、大変な野球の虫です。 そこ出会う機会があれば野球の話ばかりで、純粋で情熱的で、ち密な野球をする彼に魅せられて“交流”とは近大から投手を駒大に預けて太田監督に指導を受けさせ、駒大からは野手を預かって、私が責任を持ってバッティングを教えるという“交流”です。 こんなことは、お互いに心底から信じあっていなければできないのでしょうか。現在、広島球団で中心選手となって活躍している野村謙二郎君も近大の生駒グラウンドで練習をした1人です。 ところが昭和60年の春のリーグ戦で優勝しながら大学選手権の関西代表を決める決定戦で、近畿リーグから勝ち上がってきた国立の阪大に敗れてしまったのでした。忘れもしない6月3日。その夜、私は部員と反省会という名の話し合いをしました。 「阪大に負けたのは何か忘れているものがあったからではなかったか」。 私も反省をしました。そこで「このチームを鍛えるときは今しかない」と考え、7月1日から18日まで猛暑の中で打撃投手を使って1人当たり1万回のバッティングをさせるプランを立てたのでした。 考えてみると、これはすさまじいことです。部員たちにこのプランを説明すると、阪大に敗れた悔しさもあって「やります」という返事が返ってきました。 「次の世代のためにも必要。もう一度、原点に立って・・・」 私と近大野球部は改めてスタートを切ったのでした。部員の手はマメができて、しかもカチカチ。投手は指先の血マメをものともせず投げました。取材にやってきた記者が「親兄弟に見せられん」と「練習を見て、つぶやいたそうです。 |
|