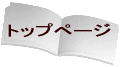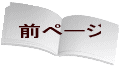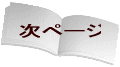| �ߑ呍�ē@���c�����@�@�hTalk�hand�@Talk�@�������w���Ҙ_�i2�j |
| �ߊ�̊��Z��w���i�A�����đ�w���{��֏����� ���ł����A���w�����[�O�̗Y�Ƃ��ČN�Ղ���ߋE��w�����A���a36�N�܂ł͒n���A���̉B�ꂽ�����ɂ����Ȃ������B���Z��w���i���ʂ����܂ł̒������������̂�A�����ď��i��A���x�͑S���̒��_��ڎw���킢�̓��X�|�B�ߑ�싅���̕��݂͏��c�������ēƂƂ��ɂ������B |
|
| �����M�̉�c�́h�c���ٌ��h�ł��Ɍ����A�֘Z����̓��J����� | |
| �u����w�싅�A���v�n�ݑO��̘b�𑱂��܂��B �@���̘A���͊��Z��w�A�ߋE�A��_�A������4��w���[�O�𗃉��Ɏ��߁A���[�O�킪�I���������ƁA�ߋE�A��_�A������3��w���[�O�D���Z�ɂ���āA3���[�O�̃`�����s�I�������߁A���̃`�����s�I�������Z��w���[�O�ʼn��ʍZ�ɒ���A�`�������W���[�����ĂΊ��Z��w����B�s�҂́A�ʃ��[�O�ɂƂ��������ł��B �@����Ɋ֑傪�܂��^���B�₪�ē���A��������^�������̂ł����A�֊w�Ƌ���A�_�ˑ�͏I�n��сA�唽�ł����B �@���a37�N�t�A���Z��w�́u����w�싅�A���v�̑n�݂ɂ��ĕ]�����Ƃ邱�ƂɂȂ�A���͂��̉�c�̍s�������������̂�Ō�����Ă��܂����B��c�͔��ɋٔ��������[�h�̒��ōs��ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂����A�܂��ɂ��̒ʂ肾�����悤�ŁA�֊w�A����A�_�ˑ�͐^�������甽�B��c�͉��X�Ƒ����A���ɋc���ٌ��ɂȂ�܂����B �@�c���͗����傩��I�o����Ă��܂����B�c���͎^���ɁB��������4��3�ŁA�Ȃ�Ƃ��u����w�싅�A���v�́A�����ɒa���B����w�싅�E�ɂƂ��āA����͈��v���ƂȂ�܂����B �@���̔N�̏t�̃��[�O��́A4��w���[�O�Ƃ��A����܂łɂ͌����Ȃ������M�̂��������������W�J����܂����B���Z��w���[�O�̕��ł͍ʼn��ʂɂ����͂Ȃ�܂��ƁA�җ��K�𑱂�������ł��傤���A�ߋE�A��_�A�����̊e��w���[�O�����Z��w�����ڎw���Ă��ꂼ��]���ɂȂ����M���������������܂����B�ߋE���[�O�̋ߑ�������ł��B �@�u�ߋE���[�O�ŏ����A3��w�D���Z�̑Ό��ɂɂ�������"�֘Z�h�Ƃ̓���ւ���Ɂv���ꂪ�����ē߂�ߑ�싅���́h�����t�h�ł����B�ߑ傾���ł͂���܂���B�e��w�������v���������̂ł��B �@�ߑ�͏t�̃��[�O��ŗD�����܂����B���Z��w�̕��͐_�ˑ傪�ʼn��ʂɏI���܂����B �@3��w���[�O�̏t�̔e�҂ɂ�����ւ���ւ́h����Ҍ����h�ł��ߑ�͏������̂ł��B�R���z���A�J��n��A����̓����������Ă����ߑ�싅���Ɛ_�ˑ�Ƃ̓���ւ���́A���ɂƂ��Ă��ꂱ���������̐킢�ł��B �@�u�_�ˑ�ɏ��Ăߑ�̗��j���ς��B����A���̑�w�싅�̗��j���B�撣���Ă��������v �@���Ƃ��Ă����������q�����́A���X�ɂ��������Č���ɂ��܂����B �@���Z��w�œ`�����ւ�_�ˑ�Ƃ̓���ւ���͐��{����ōs���܂����B�����A���Z��w�̃��[�O��́A���̋�����g�p���Ă�������ł��B���2�������������҂ƂȂ����ւ���---�B�Ȃ�Ƃ��Ă��揟���Ȃ���Ȃ�܂���B �@�Ƃ��낪��1��A�ߑ�͋������B����ł��B0��2�̃X�R�A�Ő_�ˑ�ɉ�����A�x���`�ɂ͎���ɔs��̐F���Z���Ȃ��Ă��܂����B�����A�V�͉�����̂Ă͂��Ȃ������̂ł��B |
 ���a�R�W�N�A���Z��w�ʼn��ʁE�_�ˑ�Ƃ̓���ւ���ɏ����h���i�h���ʂ������ߑ�i�C�� |
| �����a37�N�t�A����ւ���Ő_�ˑ��j���ď��i�ʂ��� | |
| �@�ߑ�Ɏv�������Ȃ��D�@���������܂����B������g��ڈ���̍D�@�h�B���͑Ŏ҂̑�F���`�N�Ƀo���g�𖽂��܂����B���݁A�I���b�N�X�őŌ��R�[�`�����Ă��邠�̑�F�N�ł��B�ނ́A�I�݂Ƀo���g�����s���܂����B���̏u�ԁA�o���g�̋�������肪�Ȃ�Ƒ别���B��������������ɁA�_�ˑ�ɋt�]���������܂����B �@���̑��킪�ő�̃��}��B������t�]�����ŏ������ߑ�́A������2����蒆�ɂ���āA���Ɋ��Z��w������ʂ������̂ł��B�X�^���h�Ő��������Ă��ꂽ�����c�A����Ɉ�ʊw����n�a�����́A�����̂�升���B�������Ă���n�a�������Ԃ�Ƃ���܂����B �@�u����ł�������ɗ��Ă�B����́A���̓��ɂȂ邩�킩��Ȃ������Z��w�̔e�҂ɂȂ��āA�_�{����ʼn��҂ɁE�E�E�v���̖��͑傫���c��̂ł��B�@�u�ēA��J���ꂽ����������܂����ˁB�g�֘Z�h����̊��z�����Ă��������v �@�u����w�싅�A���v�̑n�݂ɍۂ��āA�Ƃ��甜��ȁg�R�����h�������o���A�n�ݍH������Ă����̂�m���Ă���}�X�R�~�W�҂̃C���^�r���[�ɁA���Ƃ��畽�Â��܂����B���̗���Ƃ͂����A�`���̂�����Z��w�̈ꗃ��S���Ă����_�ˑ�싅������n�a�̋������@����ɗ]�肠��������ł����B �@���Z��w���肵���ߑ�ɑ傫�ȕω����N�������̂́A���̗��N�B�V���������Ȃ��90�l�ɂ��c��オ�����̂ł��B������f���̂���҂�������Ȃ����炢�����Ă����̂ł��B �@�u�ēA�ߋE���[�O�Ɗ��Z��w�̊Ŕ̍��ł��ˁv�n�a�������������Ƃ��������̂��v���o���܂��B�������ɁA���̒ʂ�ŁA�ߋE���[�O����́A�������U�ɂ����Ă����Ă���Ȃ������̂��A���Z��w�ɓ���ƁA�֓��̑�w����U���Ă������Z�����A�֓����R���ċߑ�ɗ��Ă����̂ł��B�ޗǂ̐���R�[�ɂ����p����ɂ�1�N���������Ђ��߂������̂ł��B �@���̋��ꂪ�o�����̂́A���ɂЂ��Ȃ��Ƃ���ł����B�ߑ傪���{��w�싅�A���̌����L�O���ŗD���������Ƃ�����܂����B���肪�������痈�������ȎO�N�ŁA�ނ͌�ɓ�C�i���_�C�G�[�j�ɓ���܂������A���̐����N��ŗD�������Ƃ��A��������ϊ��ł��ꂽ�̂ł��B �@�u���c�N�A�D���̂��j���Ɏ��͋��̘r���v���v���[���g���悤�ƍl���Ă��邪�E�E�E�v �@�u�����A���v�����~�������̂�����܂��v �@�u���̗~�������̂Ƃ́H�v �@�u�͂��B����̓O���E���h�ł��B�O���E���h���ق����̂ł��v |
 ���a�R�W�N�A�ߑ�̎�̓����o�[ �i������ēc�A�����A��F�A���c�A���{�j |
| ������R�[�̃O���E���h��90�l�̐V�������ł��ӂ�Ԃ��� | |
| �@���͑����ɉ��ʂ��Ȃ������܂����B����ƁA�����̓O���E���h�p�n�ɂ��āA���ꂱ��Ǝ��₳��܂����B�u�O���E���h�ɂ҂�����̗p�n������܂��B�A�e�͂���܂��v �@�O���E���h���~������O����A���͑����Ƀf�^�������������̂ł��B�p�n��������A������Ă��ƌ���ꂽ���́A�ߓS�Ŗ����K�[�������F�l�̂Ƃ���֔��ōs���đ��k���܂����B �@�u����R�[�ɁA�O���E���h�ɂł������ȓy�n������B�펞���ɖ������i�������j���O���C�_�[�������߂̓y�n�������̂��ߓS���w�����āA���̂܂܂ɂ��Ă���v �@���̘b�Ɏ��͔�т����̂ł��B�Ȃɂ���A�ߑ�싅���́A��p���ꂪ�Ȃ��A�������Z�O�̍L���A���������̓�싅��A����ɔ����s�̎R�{����Ȃǂ�]�X�Ƃ��ė��K���Ă����̂ł��B �@���������A�����͋ߓS�o�b�t�@���[�Y�̓�R���R�{����ŗ��K�����Ă������A���ɂ͈�R�������ŗ��K�B�ߑ傪��Ɏg���A�����[���͋ߓS�Ƃ�����茈�߂����Ă����̂ł��B�������ړ����K�ł����琶��R�[�ɗp�n������ƕ������ꂽ�Ƃ��́A���ꂼ�g���݂̍j�h�Ƃ���A�����������ɍs�����̂ł��B �@�O���C�_�[�̊����H�̓C�����ɂȂ��Ă��܂����B���n����Ă��Ȃ����������Ԃ�Ƃ����āA���̌������͎R�ł��B���A�Ȃ�Ƃ���p����ɂł���Ɗm�M���āA�����ɓ`���A��w�̕��ōw�������肵�܂����B3���i��10�������b�j�̉��i��800���~�B�����N��100���~����8�N�ԂŎx�����Ƃ��������ł����B���݂ł����̓��̊�т͖Y����܂���ˁB���͕ČR�̒��Ẫu���g�[�U�[���A������^�]���ăO���E���h����ɂ�����܂����B�싅�����͑������烂�b�R�������A�y�^�тł��B�����������ł�����A���K�Ȃǂ͘_�O�ł��B �@�����Ă����Ă������Ȉ�����A���n��Ƃł����畔���Ԃŕs�����Q�����܂����B���̉Q���܂��܂��g�債�āA���Ɂg�ē{�C�R�b�g�h�ɔ��W�����̂ł��B�@�u�����A����Ȏ����肳���āA�ЂƂ����K����点�Ă���Ȃ��Ƃ́B����Ȋē̉��ł���Ă����Ȃ��v �@�����������R�ŁA�����{�C�R�b�g���悤�Ƃ����̂ł��B���ꂪ�����̎��ɓ������悤�ł��B���������ɑ��k���܂����B �@�u����ȕ����͑ޕ����Ă�����Č��\�B��߂Ă�����Ă͂ǂ����B�`�[�����[�N�𗐂��҂����Ă͂����Ȃ��B�v �@�����̌��f�ɂ���āA�������S�B�싅���ɂƂ��Ă��Ă����Ȃ������̂��o��̏�ŁA�N���[���E�A�b�v�E�g���I�̑I���ޕ������܂����B����͒f���̎v���ł����B �@��p���ꂪ��������̂�3�N������܂����B�싅��J���͏��a35�N�B���̃Z�����j�[�ɂ͓��{����A�̍����B�v���i�̐l�j���S�悭�o�Ȃ��Ă��������āA����������Ƃ�������̂��Ƃ̂悤�Ɏv���o����܂��B �@���̐�p����́A���Z��w���肪���܂��Č���ƁA������]�҂����X�A90�l���̐V�l�����ł��ӂ�Ԃ����̂ł��B |
 ���X�ɋߑ�͑S����ɂ̂��オ��B���a�R�O�N��ɂ͊؍��������s�����B�i�������c���A�E�͌��؍��v���싅�s���O���ēE���i�����j |
| �����X40���Ԃ̒��f�őS�����e�̖�]�͑ł��ӂ���� | |
| �@���a41�N�t�̃��[�O��ŋߑ�͗D�����܂����B���Z��w�ɓ������̂�37�N�H�̃��[�O��ł�����8�V�[�Y���ڂł����D���ł����B�g�œ|�����Z��w�h�ɖڕW�����ڂ�A���������ɂ��Ă����ߑ�ɂƂ��āA����܂łɂȂ����͂ȃ`�[���B����͏��R���o�g�̎R�����v�N�B�R���N�̓h���t�g���x2�N�ڂ̏��a41�N�ɔN2��̃h���t�g������܂����B����2��ڂ�1�ʂő�m�i�����l�j�Ɏw������ē��c�B��m����N���E���E�����A��C��3���c��16�N�ŒʎZ103��������������ł��B����ɗL���ʐ��N�i�̂������j�A�������N�����܂����B�L���N�̓��b�e�̎�C����ēɁB�����N�͌��݃_�C�G�[�̃R�[�`�B �@���̂Ƃ��̃����o�[�́A�Љ�l�싅�Ǝ��������Ă������邱�Ƃ͂Ȃ��A���݂ł��ߑ�j��ŋ����Ɗm�M���Ă���̂ł��B���̃`�[���łȂ牤�҂ɂȂ��A�Ƒ�w�싅�I�茠�ɗՂ킯�ł��B����͓V�����̖�]�ɔR���Ă̓���ł����B�u���̃`�[���Ŋ֓����ɕ�����͂��͂Ȃ��B�֓��Ȃɂ�����̂��I�v �@����ȋC�����ł����B�����āA���J������ƁA�v�f�ʂ�ɏ����i�݁A�����œ���Ɗ�����킹���̂ł��B �@�����͋ߑ傪2��0�̃X�R�A�ŗD���ɐi�߂Ă��܂����B�O�����I����ă��[�h���Ă���̂ł�����A���ƈꉟ���B �@�Ƃ��낪6����I������Ƃ���ʼnJ���~��o���A���ꂪ���������Ȃ��Ē��f�B���̒��f��10���A20���Ɖ߂��A30�����o�߂��܂����B���͓��R�A�Ď�����\�z���܂����B������ł�����R�[���h�Q�[���͂���܂���B�ǂ��݂Ă������A�Ď����ł��B �@����Ȃ̂ɁA�܂��ҋ@�B�Ď����̋C�z������Ȃ��A�Ȃ�ƒ��f����40����Ɏ����ĊJ�B���̎��A����ȗ\�����������̂ł��B �@���̗\�����I�����Ă��܂����̂ł��B�O��肪�ŋ���ǂ��������ہA���ȃO���E���h�ɑ�������ē]�|�B���ꂪ�����ƂȂ��ċt�]�����B����ɓ��{���������Ă��܂��܂����B���̏�ʂ́A���݂��Ȃ����̔]���ɑN���Ɏc���Ă��܂��B �@�u�J�ɂ��40���̒��f���Ȃ�������B�Ď����ɂȂ��Ă�����E�E�E�B�Ȃ�40���Ԃ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��v �@���ꂱ��l����ƁA���ւ̋A�r�A�����������܂��ĂˁB���O�ŁA���O�ł��܂�܂���ł����B �@�������A���̂���܂ł́g�싅�l���h��U��Ԃ��Ă݂܂��ƁA���̏��a41�N�̑�w�I�茠�ŁA�������D�����Ă����Ƃ�����A45�N�Ԃ����j�t�H�[���𒅂Ă͂��Ȃ������ł��傤�B �@�g��萬�A�h�Ƃ������ƂŁA��p�҂Ƀo�g���^�b�`�����Ă��������m��܂���B �@40���Ԃ̒��f�ɂ��J����ɂ����閳�O�̔s�킪�A���̓��u���������Ă錴���ɂȂ��āA�傫�ȗƂƂȂ����̂ł�����B�u�Ȃ�A����ȍ�v�Ƃ����C�����ŁA�������g�����������̂ł��B |
 �L���ʐ��O�ێ�i�̂����b�e�j��̊���ŏ��a�S�P�N�͑S���{��w�I�茠�̌����܂Ői�o�A�ɂ���������ɔs���B |